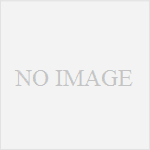涙
学生の時に出会った、ある女の子は自分の好きな時に涙を流す事ができる才能を持っていた。
それはまったく素晴らしい才能だった。いついかなる時でも、数十秒もあれば彼女はすぐに涙を見せることが出来た。
僕等は入学式で席が隣になったきっかけで何となく仲良くなったのだ。
初めて彼女が泣くのを見たのは、学食でランチを食べていた所だった。
「いくわよ」と彼女は言って、目の前でその技を気前よく見せてくれた。
その技はまるで、長期にわたる地殻変動を記録したビデオの早回しを見ているかのようだった。
魅力的な表情が消え、徐々に顔を崩し始める、そして突如として目から一筋、水滴が湧き出たかと思うと、
すぐさま、とめどなく頬を涙が伝い始めた。やがて手をあごにそえ顔の安定を得るとさらなる涙が両目から流された。
その間ずっと彼女は静止し、僕をじっと見て目をそらすことがなかった。
鼻をくすんくすん言わせながら「どう?」と聞かれてしまえば、「いや、すごいね」と僕は言うしかなかった。
僕もどちらかというと涙もろいし、人前でも関係なく泣くタイプだけど、昼間ののんびりとした学食で、
理由もなく大勢の前で涙を流すことなんでまず無理だ。
コツはね、と彼女は言う。
「集中するのよ、なんでもいいんだけど」とお米がまだ半分ぐらいのった定食のお皿を手にとって言う。
「あぁ、お米ってなんて素晴らしいんだろう。私あなた達の一粒一粒のおかげで今こうして生きているの」と例えばものすっごく強く思うわけ。
それから、ここが肝心なんだけど、それを想いをしっかり溜めるの。しっかり握って外に出て行かないようにしないとダメ。
わかる?少しももらしちゃだめよ。さぁやってみて」
一応納得して、僕はお米の事を考える。しかし一粒も涙は出てはこない。
「だから、無理だって」と僕は答える。
彼女は女優としての才能があったのかもしれなかったが、彼女はそんな事はどうでもいいように振る舞っていた。
その代わり生きるための武器として存分にその能力を利用した。
その結果、彼女は自分で思っているよりもずっと美人だったから、どうすれば彼女と付き合えるだろうか?という
見知らぬ男からせっぱ詰まった相談を少なからず僕は受けることになった。
それと同時に女性陣による彼女に対する攻撃的な嫌みも多く聞くことになった。
都合よく涙を流される彼女達にしてみれば、腹の立つ事も多かったんじゃないかと思う。
そんなある日、彼女から深夜に電話がかかってきた。
たしか2時頃だったと思う、僕はもう誰がみても寝ているねといえる程しっかり寝ている状態だった。
若くて見当違いの考えばかりもっていたとはいえ、僕等はお互いに異性としての魅力を少しは感じていたのだと思う。
でも、そういう異性の友人関係というのは貴重なものだ。
だから、こうして時々電話がかかってきて話をする間柄だった。
電話に出るなり彼女はこういった。
「あなた、何か泣かせる話をしてくれない?」
「そんな事なら、君ならいつでも泣けるじゃなかったっけ、いつか見せてくれたじゃないか」
「泣きたいんじゃなくて、私は泣かせる話が聞きたいのよ。今すぐに」
仕方なく、僕はとって置きの話をしてあげた、自分が飼っていたポリドール犬がいかにして自分と仲良く暮らしていたか。
それからどのようにして犬が年を取り、老衰して落命したか。最後には月夜に立ちすくみ、野生に帰る象徴的な瞬間の話までした。
僕は話ながら涙ぐんでいた。
「よくわからないけれど、その話のポイントはあながた犬が大好きだったってことよね」と冷たく言った。
僕は彼女の冷たい返答に怒りを若干覚えながら、「そうだよ、その通りだよ」と目頭を抑えながら言った。
「泣くポイントとかタイミングって本当はなんなのかしら」と彼女は言った。
彼女が何を聞きたいのか良くわからなかったが、とにかく僕はもう疲れてきたので、質問に答えて電話を切ることにした。
「人それぞれだし、僕にはよくわからない。でも、内に気持ちを踏みとどめて泣く人とそうでない人がいると僕は思っている。
子供が、かって気ままにどこでも泣くのは感情のコントロールができないからと言うけれど、大人だって同じさ。
感情のコントロールが出来ない人が泣くとされている。そしてそれはみっともないことだと言われる。
でもね、僕が言っているのは、時々、大人も踏みとどめた上で、泣いてもいいんじゃないかと思っているんだ。
君がいつかやってくれたみたいにね。さぁもう遅いし寝ようよ。明日話そう」と僕は行った。
「今、外にいるんだけどちょっと出てこない?」と彼女はふいに言った。
「外ってどこだよ」
電話をもったまま僕は一回転してベッドで仰向けになった。
「外ってあなたの家の前よ」と彼女はすんなり言った。
慌てて、着替えをして、大急ぎでドアを開けた。
まったく何考えているんだと僕は思った。
僕等はかれこれ1時間以上も電話で話をしていたのだ。
外に出ると、道路の向こうのチューリップの花壇のふちに彼女は座っていた。
遠くから見れば演技でもなんでもなく、ただ泣いているように見えた。
僕は彼女のところに走りよって声をかけた。
「何かあったの?」
「何かあったにきまってるじゃないの」と彼女は言う。
「このタイミングはどうなのかな」と彼女は言った。
「夜中に、知り合いに、今唯一頼れる人のところに言って、これからわがままを言うポイントとタイミングの事なんだけど」
僕は彼女の横に座って、ゆっくりと足をのばし、左の足を右の足にのせてそれから右ひざをさすった。
「十分に泣いていいタイミングだと思う」と僕は言った。