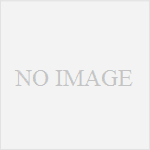パン屋
街の中で、歩みを止めてパン屋に入る。まだ午後も早い時間。
店に入るなり、すぐに香ばしい匂いが鼻をよぎる。
クロワッサンとコーンの乗ったパンをトレイに乗せる。
そしてレジでコーヒーも注文する。それから店に備え付けられたカウンターに座る。
お昼を過ぎているからなのか、天気のせいかこの時間の客は僕だけだ。
それと20代前半ぐらいの女性の店員が一人ぼんやりと立っている。
店内はショパンとおぼしきピアノが小さく鳴っている。
そして僕は濡れたコートを脱ぎ、ようやく落ち着いた気分になる。
カウンターから見える窓をつたう雨のしずくが見える。
少し前から外では雨が降り出している。
そのいくつかの雨のラインが、ある記憶を捕らえる。
もの思いにふけって、窓を見つめる、そして別の日の別の窓を思い出す。
あのころ僕と彼女はまだ学生で、彼女が乗るはずの飛行機を空港で待っていた。
彼女はこれから数ヶ月遠くの学校に通うはずで、先に行った両親に飛行機で追いつくはずだった。
カウンターに並んで座り、雨の中、順々に飛び立つ飛行機を見つめながら、カウンターの下で手を伸ばして彼女の手を握った。
彼女の手は僕よりも暖かく、そしてずっと小さかった。
雨のせいで発着が遅れていたから、長い時間、出発ぎりぎりまで僕らはそうしていられた。
あの瞬間はなんて素晴らしく、魔法のような時間だっただろう。
店員さんが私の横に来て、コーヒーのおかわりを入れに来る。
それから「よろしければアンケートをお願いできますか?」と彼女は私にB5サイズの紙のアンケートを渡す。
うなずいて、アンケートを上から順番に記入していく、好きなもの、良く読む雑誌、良く飲む飲み物…
途中まで書いた所で手を止める。鉛筆を置いて、アンケートをふせる。そして席を立ちレジへ向かう。
「パンの木を作りません?」と僕は言う。
「え?」と彼女は驚く。
そういって僕は店内を回り、気に入ったパンをトレーに乗せ始める。
「大丈夫です。ただ棚にパンを乗せるだけです。きっと木にパンがなっているように見えますよ。」と僕は言う。
それから僕は背伸びして棚にあった賞状や写真立てを彼女に渡す。
そして、一番上に天然酵母パンを丁寧にまっすぐに置く。
次の段にはバスケットを逆さまに置いて、その上にソーセージパンを重ねる。
その左の棚にはアンパンがいくつかぶら下がるようにして、整えて置く。
黙って見ていた店員さんも観念して、脚立を持ち出し、一緒になってパンをきれいに重ねて行く。
最後に棚と棚の間に、パンをこねるための長めの棒を置いて木の幹にする。
そして二人でカウンターに座り、出来たばかりのパンの木を眺める。
「面白いですね」と彼女は言う。
「良い出来ですよ」と僕。
「一つ聞いていいですか」と彼女は言う。
「どうぞ」
「パンの木って本当はパンがなっているんじゃないんでしょう」と彼女は言う。
「ええ、そうです。その通りです」と僕は彼女を見て答える。
やがてお店を立ち去る時間が来る。レジで飾り付けたパンの代金を払い、書きかけのアンケートを渡す。
そのパンの代金を断りながら、彼女はアンケートを見る。
「お近くの方ではないのですね」と彼女は言う。
「ええ、でも春になって近くに来ればまた寄るかも知れません」と僕は言う。
彼女は去り際に僕を呼び止める。そして出来立ての暖かいパンを手渡す。それから
「まだ雨がふっていますから、気をつけてくださいね」と窓の外を指さして僕に言う。