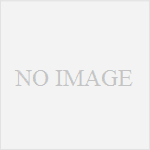万里の長城 ノート1 フランツ・カフカ
死ぬ前に、カフカが全ての作品を捨ててくれと頼んだ友人マックス・ブロートがそうしなかったおかげで、今では誰もがカフカの小説を読む事が出来る。たられば話は意味がないけれど、もし「変身」や「城」といった20世紀を代表するカフカの作品がなければ、小説も今とは全然違ったものになっていたかもしれない。そう思うとよくやったマックス・ブロートという気がしてくる。もし自分が同じ事をされたら腹立つだろうけど、きっとこの人中身読んじゃったんですよ。そして、これは捨てるわけにはいかないと思ったに違いない。だからカフカは選んだ人を間違えたのかもしれないし、そうなるのが分かってたかのどちらかってことだ。
そのマックスが残したものは完成したカフカの小説だけではなく、習作もノートとして残っていた。それが翻訳されたのがこの「万里の長城(ノート1)」である。
このカフカ工房(ノート)をのぞき見してみると、カフカがどういうふうに小説を書いていたのかが分かる。実際の万里の長城で採用されていたらしい分離工法(あまりに広大な工事区域のために、果てしなく続く労働の空しさに、絶望感をもってしまわないよう、同じ場所に留まることを禁止し、1000メートル完成すると作業班は距離の離れた別の現場に移動させられた。)のように、頭から書かず、ばらばらに書いたものを寄せ集めていた事が分かる。この本にはカフカが試みたいくつかの書き出しのバージョンや面白いのに一章分しかないものもある。ここに収められたものは結核と診断された1917年以前のもの。
小説の内容やカフカという名前から、偏屈であまり誰とも口を聞かず、黙々と自分の世界と向き合っていた男だという印象をもっていたが、これを読むとがらりと変わってしまった。カフカは恋をしていたし、ユーモアのセンスも抜群だった。これを読んだ後では、今までは想像もつかなかったカフカの笑顔を想像することができる。たとえば、思いついたばかりの着想をかかえながら、チェコの石畳の道を小脇にノートをかかえ、書斎のある家まで歩くカフカの笑顔を。