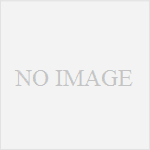体の贈り物 レベッカ・ブラウン
いくら翻訳している柴田元幸さんがこの本は読んでみないと魅力をわかってもらえないと言っていても、最初はやはり手に取るのに気が引けた。余命いくばくもないエイズ患者の闘病生活を支えるホームケア・ワーカの話だけで構成されているらしい。だから、どうしても気持ちが重くなって本棚にもどしてしまうのである。結局、出てすぐ買って気にはしていながらも、そのままだらだらと後回しにしてしまい、文庫が出て持ち歩くことができるようになってから、読み始めるような事になってしまった。
ここに書こうとしているのだから、言わずもがなで、この本は本当に素晴らしい本だった。まず最初の短編「汗の贈り物」を、通勤の電車の中で朝、半分寝ぼけながら ぼんやりと立って開いて読んでいたら、いっぺんに目が覚めた。この本は、とそのときのぼくは思った。こんな風に適当に読んじゃいけない本だ。そう思って、とりあえずすぐに本を閉じて、座席が空く事を待つ事にした。もし空かないならどこかの駅で降りて読もう、何だったら降りる駅を通り過ぎても構わないとまで思った。いつもぼくは遅刻しないようにわりと早めの電車に乗っていることだし。
小説の神様の力なのか、次の駅で運良くぼくの目の前の席が空いた。鞄をおろし、腰を落ち着け、ゆっくりと深呼吸をして読み始めた。誰も出て来れないという病棟から脱走したスーパーエドが活躍する「動きの贈り物」では、ガッツポーズをして高く手をあげたくなった。「死の贈り物」では優しさと辛さと痛さを共有した。レベッカブラウンの書く淡々と続く、読みやすく装飾を廃した文章は、いつもなら決して触らせない心の柔らかい部分まで、まるで子守歌のようにやすやすと侵入して来ていた。
終盤の「希望の贈り物」まで来たとき、ついに涙がこらえ切れなくなった。体を「く」の字になるようにして、座席に突っ伏して泣いた。それは安っぽい映画を見て流すような安い涙ではなかった。逃れようのないリアルな死を前にして、消え去るものと残されたものを感じ取り、心が揺さぶられたから出てきた涙だった。